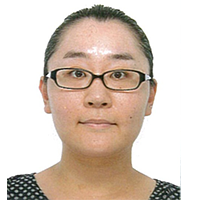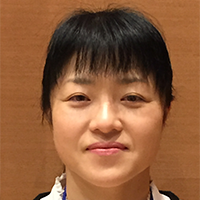災害軽減対策を専門とするバングラデシュ災害予防センター(BDPC)の創設者。2002年に国連笹川防災賞を受賞した唯一のバングラデシュ人。オーストラリア災害対策局防災大学卒業後、1972年から1991年まで災害救援及び復興事業に従事し、災害対策に関する基礎的研究を推進してきた。災害対策は、事後対応よりも事前のリスク軽減が大切だと考え活動している。バングラデシュで広く使われている「バングラデシュ災害対策ハンドブック」など、著書多数。バングラデシュの政府機関と防災関係のパートナー、国内最大のフォーラムである、NGO諮問委員会会長。


ナシーム・シャイク氏は20年間ほどレジリエントで持続可能な発展における市民 参加型の女性リーダーシップを推進してきた。1993年の地震後、マハラシュトラ のオスマナバッド地区で女性と一緒に働き始め、2001年のグラジャ-ト地震後に 災害後の復興に貢献した。女性市民の交流学習トーレニングや、国の主要人物と の対談を主催している。更に、インドだけでなく、ケニア、ナイジェリア、フィ リピン、タイ、ネパールでも、持続可能な農業、健康、水と衛生、災害レジリエ ンスといった分野において、市民参加型の活動や女性リーダーシップトレーニン グなどにも取り組んでいる。

ActionAidの国際部部長でレジリエンスと気候変動問題に従事している。インドの ニューデリー市に拠点を置きながら世界中の国で、災害や気候変動に関わる政策 提言や企画のサポートをしている。以前、アジアとアメリカ大陸地域の災害緊急 対応の調整を担当していた。3年前から地球市民社会のための防災ネットワーク (GNDR)の理事、CAN Internationalの適応・喪失・損害グループの共同代表を務 めている。

20年以上に渡り、非政府セクターにおける災害リスク管理に従事。災害応急対 応、復旧・復興、事前準備、災害軽減に関するプログラムを、アフリカ・アジ ア・欧州の広範囲で展開した経験を持つ。2007 年 6 月には、地球市民社会のため の防災ネットワーク(GNDR: Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction)の初代議長に就任。GNDR以前は、英国の国際 NGO である Tearfund の理事として活躍。災害関係業務を広く統括するほか、政府・政府間・ 非政府セクター間において、貧困削減に資する防災概念の普及および実践を推進 する指導的な役割を担った。

マヌー・グプタ氏はNPO法人SEEDSの共同創立者・代表で、アジアにおいて防災 と災害救援と復興活動をしている。地域密着型災害管理の博士号を持ち、アジア 18ヶ国のNGOのネットワークを持つアジア防災・災害救援ネットワーク (ADRRN)の理事を務めている。現在は地球市民社会の防災ネットワーク (GNDR)と国連国際防災戦略事務所のレジリエントシティーズキャンペーンの 運営委員会の一員として活動している。近年、政府と市民社会のパートナーシッ プを通して、一層の説明責任を確保するための市民の声の重視を訴えている。








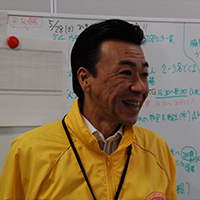


環境問題に関する講演、執筆、コンサルティング、異業種勉強会等の活動を通じて、 「伝えること」で変化を創り、「つながり」と「対話」で、しなやかに強く幸せな未 来の共創をめざす。経済成長を前提としない幸せのあり方や持続可能性をベースにし た新しい社会のシステムについて学び、考え、対話する研究会を主宰。ブータン王国 国王陛下の勅令により設立された「豊かさと幸福」の実現を考える国際専門家作業グ ループでも研究を進めている。主な著訳書に、『「定常経済」は可能だ!』、『不都 合な真実』など多数。


東日本大震災から、温厚で優しい自閉症の次男が笑顔を失くし、突然暴れ出すよ うになる。地域に同じような状況となっている障がい児・者がいることを知り、彼 らの笑顔を取り戻し、安らげる居場所を作りたいと、2013年1月、親達と一緒に 「本吉絆つながりたい」を結成し、事務所を自宅に置き事務局をしている。

1965年釜石市生まれ。釜石市で本業の菓子店を営む傍ら、まちづくり活動を経 て、2004年に特定非営利活動法人@リアスNPOサポートセンターを設立。以降、 様々な活動を行ってきたが、2011年東日本大震災により事務所を含めて被災し た。それ以後は被災地のNPOとして「被災者が主役の復興」を目指して活動を再 開している。震災後に岩手県内の中間支援NPOが連携し、設立されたいわて連携 復興センターの代表理事を務める。
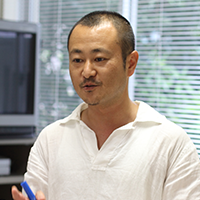
学生時代、国際交流NGOピースボートの世界一周クルーズに参加。その後、職員 として約60カ国を巡り、洋上平和教育プログラムや国際協力を担当。東日本大震 災後、ピースボート災害ボランティアセンターを立ち上げ、東北やフィリピン台 風の被災地でのコーディネーターとして活動する。第3回国連防災世界会議では、 「2015防災世界会議日本CSOネットワーク(JCC2015)」事務局として、仙台市 内の団体との調整・協働を担当する。
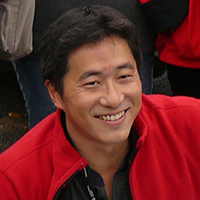
国際基督教大学にて国際機構論と EU 法を学び、ロンドン大学において EU および 非市民の権利に関する研究。2006 年より国連難民高等弁務官 (UNHCR)駐日事務所 にて、政府機関との資金調達・交渉、政策提言、NGO・市民社会との連携強化を担 当。2011 年 3 月には東日本大震災を受けて国連災害評価調整(UNDAC)チーム、そ して 4 月から 5 月にかけてジャパン・プラットフォームに出向し、情報収集・発信 を行った。


東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター・特任助教。北海道大学大学 院文学研究科博士後期課程修了、博士(文学)。専門は災害社会学、地域社会 学、防災教育。北海道上川郡剣淵町出身。北海道南西沖地震を奥尻島で経験した ことをきっかけに、災害復興、地域防災に関する研究を志す。防災教育活動を北 海道各地で展開しているほか、東北津波被災地において、奥尻島の復興プロセス に関する情報提供も行っている。

発災当時は、海や川に隣接していた石巻市立湊第二小学校の教頭。児童や地域住 民の避難誘導を行い、避難所となった同校の避難所運営の中心的役割を担った。 震災前、湊第二小学校は他の小学校と同じく、毎年、避難訓練や親御さんへの引 き渡し訓練を実施。その中で体が不自由な方の避難方法などを考えていた矢先、 今回の震災となった。2012年3月、小学校を定年退職。2013年7月よりみらいサポ ート石巻のスタッフとなり、語り部として活動をはじめた。











1977年生まれ。2001年にNHK入局。「ニュースウオッチ9」リポーターとして主 に事件・事故・災害現場の取材を担当。’10年、経済ニュース番組「Bizスポ」キャ スター。’12年より、アメリカ・ロサンゼルスにあるUCLAで客員研究員。日米の 原発メルトダウン事故を追ったドキュメンタリー映画「変身 Metamorphosis」を 制作。京都国際ドキュメンタリー映画祭特別賞受賞。’13年よりフリーラン ス。’14年よりTOKYOMX「モーニングCROSS」キャスターもつとめる。市民投稿 型ニュースサイト「8bitNews」主宰。淑徳大学客員教授。

東京都三宅島に生まれ、噴火災害で2度被災する。1983年の噴火では溶岩流で自 宅が埋没し、避難所、仮設住宅の暮らしを経験する。2000年の噴火では4年5ヶ月 もの長期避難生活を体験した。この災害の避難中から住民組織での活動を開始。一被災者として長期避難中のコミュニティ維持を支える活動を行う。2005年の全島避難解除をきっかけに「ネットワーク三宅島」を創設。2010年(一社)減災・復興支援機構を設立して活動中。